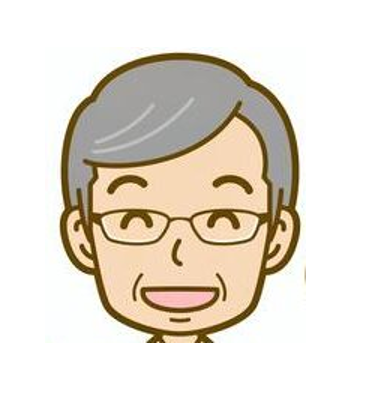2023年、終の棲家にと、一条工務店のグランスマート平屋を新築しました、シニアライフビギナーです。まだタイで現役サラリーマンをやっていますが、来年春には本帰国の予定です。帰国後は、”ちょっとかわった家の㊙アップグレード”をあれこれ企んでおります(← 妻は警戒してますが・笑)。
さて、今日は家の外を彩る”鎖樋”についてのお話しです。
くさりとい、くさりどいと読みます。英語ですとrain chain。
鎖火(くさりひ)と呼ぶこともあるようですが、鎖樋が正式名です。
通常のパイプ型の雨樋と違って、鎖樋ですと鎖を伝って地上に降りて行く雨水の様子を見ることが出来ます。
古くはお寺や和風建築でよく目にしましたが、ハイドロテクトタイルのモダンな住宅にもきっと似合いそうな気がします。
何と言っても風情を感じることが出来ますし、雨の日も楽しめそうです。

そこで、AIにお願いして描いてもらったものが↓これです。
『既設の雨樋と入れ替えて下さい』と依頼しましたが、識別が出来なかったのか、鎖樋の横に残ったままです。ちゃんと鎖の真下に砂利を入れた受け皿があって、なかなかセンスのよい絵を描いてくれました。

こちらは、ウキペディアからお借りした写真ですが、いいですねー!
雨が待ち遠しく思ってしまうこと間違いないですね! 


以下、一般的な情報になりますが、鎖樋についての解説になります。
鎖樋を採用するメリットとは
家づくりを考えるときに意外と見落としがちなのが「雨樋」のデザインです。
普段はあまり目立たない存在ですが、実は外観の印象や暮らしやすさに大きく関わっています。
その中で最近少しずつ注目を集めているのが 「鎖樋(くさりとい)」です。
鎖やカップ状のデザインを使い、雨水を美しく導く仕組みです。
古くはお寺や和風建築で使われてきましたが、今ではモダンな住宅にも取り入れられるようになってきました。
デザイン性が高い
鎖樋は「隠す」雨樋ではなく、「見せる」雨樋。
鎖やカップを伝って水が流れ落ちる姿は、建物の外観を引き立てるアクセントになります。
和風にも洋風にも合わせやすく、住まいにちょっとした遊び心を加えてくれます。
軽やかで開放的
パイプ式の縦樋がない分、外観がすっきりして軽やかに見えます。
特に庭やアプローチに面した場所に取り入れると、圧迫感がなく、外とのつながりを感じやすくなります。
雨の流れを楽しめる
雨の日、鎖をつたって水が静かに落ちていく姿は、どこか風情を感じさせてくれます。
まるで水琴窟の音色を楽しむように、自然を暮らしに取り込む効果があります。
「雨の日が少し楽しみになる」そんな体験を与えてくれるのも鎖樋の魅力です。
施工とお手入れが簡単
鎖樋は通常の縦樋よりも部材が少なく、施工が比較的シンプルです。
また、パイプ式のように落ち葉やゴミで詰まる心配がほとんどありません。
定期的な清掃が不要に近く、経年劣化しても交換が容易なので、長く使いやすいという点も見逃せません。
❄ おまけ:北国でのメリット
寒い地域では、パイプ式の縦樋に水が残って凍結し、膨張して破損してしまうことがあります。
これが冬場の大きなトラブルになるのですが、鎖樋なら水が溜まらないため、凍結による破損の心配がほとんどありません。
また、雪やツララの重みで壊れるリスクも少なく、雪解け水を自然に流すことができる点も安心材料です。
寒冷地にお住まいの方にとっては、これはちょっとした「ボーナス的な利点」と言えるでしょう。
注意点も忘れずに
もちろん良いことばかりではありません。
大雨や強風のときには水が鎖から飛び散りやすく、泥はねの原因になることもあります。
そのため、鎖樋の下には 水受け鉢や砂利、雨水桝 を設けておくのが一般的です。
まとめ
鎖樋は、
- 外観を引き立てるデザイン性
- スッキリとした開放感
- 雨の日の風情
- 掃除が楽で長く使いやすい
といったメリットがあり、さらに北国では凍結に強いという安心感もプラスされます。
「ちょっと人とは違う住まいにしたい」「自然を感じる暮らしを楽しみたい」という方にとって、鎖樋はとても魅力的な選択肢になるはずです。