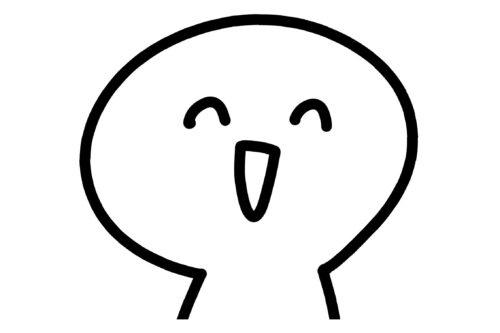タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナーです。
半世紀近くサラリーマン生活を送る中で、「運」というものの存在を強く感じてきました。
ただ、それはコインの裏表のように偶然で決まる単純なものではなく、「運はそれをどう捉えるかで決まるもの」と実感しています。

今日は、昨日の投稿でちょっと触れました松下電器の創業者”松下幸之助氏”のエピソードを振り返ってみました。
私が勤める会社でも心がけている大事なお話しです!
松下幸之助と「運がいいですか?」――採用面接に込められた深い意味
経営の神様と呼ばれる松下幸之助。彼が築き上げた松下電器(現パナソニック)は、戦後の日本経済を牽引し、世界的な企業へと成長しました。その成功の裏には、卓越した経営手腕や独自の哲学だけでなく、人材に対する鋭い洞察がありました。
数ある逸話の中でも特に有名なのが、学生を採用する際に「あなたは運がいいですか?」と尋ねたというエピソードです。
面接での一言が意味するもの
通常の面接であれば、志望動機や特技、性格、将来の目標といった質問が並びます。しかし松下幸之助氏は、まず「君は自分が運がいいと思うか?」と聞いたといいます。意外な質問に戸惑った学生も少なくなかったはずです。
この質問に対し、「運が悪い」と答えた学生は、その時点で不合格にしたと伝えられています。一方、「自分は運がいい」と答えた学生は、採用の対象となったのです。
では、なぜ幸之助氏は「運の良し悪し」に着目したのでしょうか。
運を信じる姿勢がもたらす力
幸之助氏自身、決して恵まれた境遇に生まれたわけではありません。幼い頃に父を亡くし、家業も傾き、わずか9歳で丁稚奉公に出されます。体も丈夫ではなく、病気に苦しむことも多かったそうです。しかし、そうした困難を乗り越えながらも「自分は運がいい」と語り続けたそうです。
「運がいい」と考える人は、同じ出来事に直面しても前向きに捉え、そこから学びやチャンスを見出そうとします。逆に「自分は運が悪い」と思う人は、失敗や困難を不運のせいにしてしまい、成長の機会を逃してしまう。
幸之助氏は、人の成功に必要なのは能力や学歴だけでなく、「物事をどう捉えるか」という心の姿勢だと見抜いていたのでしょうね。
企業経営に必要な人材像
松下電器は、戦後の混乱期から高度成長期に至るまで、幾度も試練に直面しました。資材不足、技術的課題、国際競争の激化――こうした困難を前にしても、社員が「自分たちは運がいい」と思えるかどうか。それは、諦めずに挑戦し、工夫し、最終的に成果を勝ち取る大きな原動力になったはずです。
幸之助氏は、社員に「成功するかどうかは能力よりも、運を信じる心にかかっている」と繰り返し説いています。
つまり、採用面接で「運がいいですか?」と尋ねるのは、単なるユーモアでも突飛な思いつきでもなく、経営哲学そのものを反映した質問だったのですね。
心の持ち方が人生を変える
心理学的にも「自分は運がいい」と思う人は、前向きで社交的な行動を取りやすいとされています。積極的に人とつながり、偶然の出会いをチャンスに変えるのです。これは現代で言う「セレンディピティ※」を掴む力に近いものかもしれません。
逆に「自分は運が悪い」と思い込んでいる人は、消極的になり、挑戦を避け、せっかくの機会を逃してしまう。つまり「運」は単なる偶然ではなく、その人の思考や行動パターンを決定づける要素でもあるようです。
現代への示唆
AIやグローバル競争が進む今、企業が求める人材はますます多様化しています。
しかし本質的な部分では、幸之助氏が説いた「運を信じる力」の価値は変わりません。
未知の課題に直面した時、「これは自分にとって新しいチャンスだ」と考えられるかどうか。それが、新しい発想や革新を生み出す原動力になるのでしょう。
私たち一人ひとりにとっても、このエピソードは示唆に富んでいると思います。
日常の小さな出来事に対して「ついていない」と嘆くのか、「まだ良かった」「これで学べた」と前向きに捉えるのかで、その後の行動は大きく変わるでしょう。
おわりに
松下幸之助氏が学生に投げかけた「あなたは運がいいですか?」という問い。それは単なる就職試験の一幕ではなく、人生をどう生きるかを問う哲学的なメッセージでした。

自分の運を信じ、前向きに歩む人こそが、困難を越え、成功を手にする。
松下幸之助氏が残したこの教えは、時代を超えて今もなお、私たちに大切な気づきを与えてくれています!
予期せぬ偶然によって、価値あるものを発見したり、幸運をつかみ取ったりする能力や、その結果のことを指します。
具体的には、ペニシリンの発見や、万有引力の法則の発見などがセレンディピティの例として挙げられます。
AIが作り出す間違った答え(ハルシネーション)にも、実は面白いヒントが隠されているかも知れませんね!