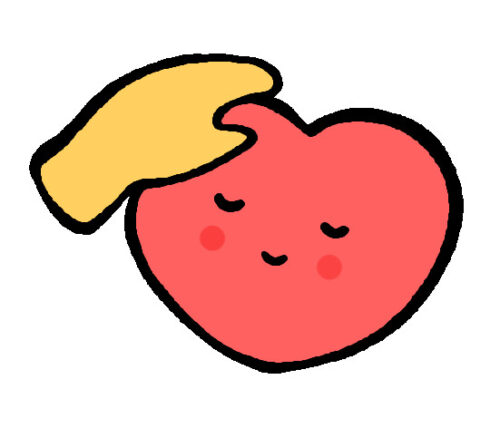タイ在住32年になります、現役サラリーマンのシニアライフビギナー66歳です。
数日前、”血糖値がやばいことに!”なる記事を投稿させて頂きましたが、その後で、「健康は天から与えられるものではなく、自らの努力によって得るもの」と説いていた貝原益軒の『養生訓』のことを思い出しました。
今日は、早速おさらいです!
彼は、私の生まれ故郷の福岡県出身です。
貝原益軒が遺した、心身の健やかな生き方
1713年、江戸時代中期に儒学者・貝原益軒(かいばら えきけん, 1630–1714)が著した『養生訓(ようじょうくん)』は、当時としては画期的な「健康長寿のための実践書」です。
単なる医学書ではなく、日々の暮らしの中で心と体を整えるための心得が、平易な言葉で丁寧に説かれています。
著者・貝原益軒とは
福岡藩に仕えた儒学者であり、教育者・本草学者でもあった益軒は、晩年に至るまで旺盛な執筆活動を続けました。
彼の思想は、朱子学を基盤としながらも、実生活に根ざした「実学」を重視していた点に特徴があります。
『養生訓』の内容と特徴
『養生訓』は、老若男女を問わず、誰もが実践できる「養生=健康維持の方法」を説いた書です。内容は大きく以下のようなテーマに分かれています:
- 飲食の節制:食べ過ぎ・飲み過ぎを戒め、季節や体調に応じた食事を勧める。
- 心の持ち方:怒りや欲望に振り回されず、穏やかな心を保つことが健康につながると説く。
- 生活習慣:早寝早起き、適度な運動、清潔な生活など、日々の習慣が健康を左右する。
- 老いとの向き合い方:老化を自然なものと受け入れ、無理をせず、心身をいたわる姿勢を重視。
益軒は、「養生は自分のためだけでなく、家族や社会のためでもある」とし、個人の健康が広く社会全体の安定につながるという視点を持っていました。
現代に通じる『養生訓』の教え
300年以上前の書物でありながら、『養生訓』の教えは現代にも通じるものばかりです。
特に、ストレス社会に生きる私たちにとって、「心の養生」の重要性は再認識すべきポイントです。また、益軒は「健康は天から与えられるものではなく、自らの努力によって得るもの」と説いています。この自律的な健康観は、現代の予防医学やセルフケアの考え方にも通じています。
昨日、お医者さんに宣言された”糖尿病予備軍”を、今度こそ真摯に受け止め、『養生訓』の教えに沿ってシニアライフを健康に過ごしたいと思います!
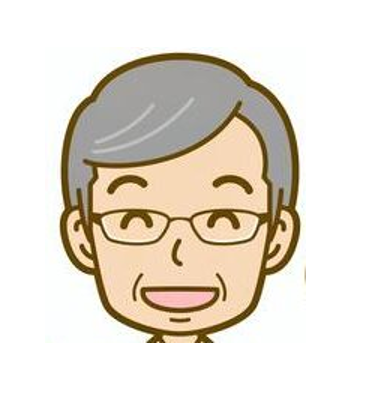
それでは、いい日でありますように!
Have a Nice Day!